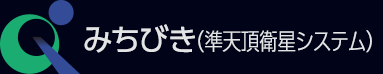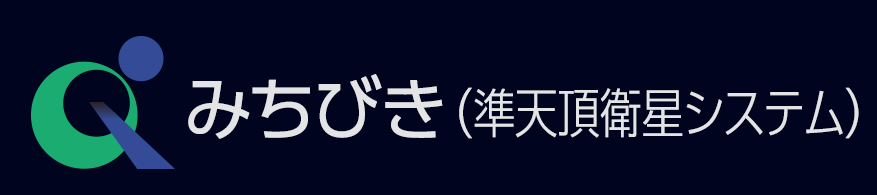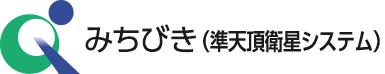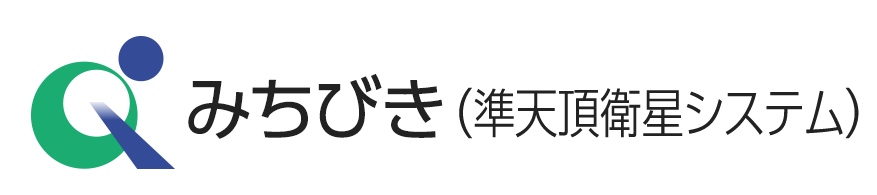日本宇宙フォーラム 吉冨 進:アジア・オセアニアの重要インフラとして定着してほしい
現在は一般財団法人日本宇宙フォーラムで常務理事を務める吉冨進氏は、JAXA(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構)在籍中にみちびき初号機のプロジェクトを立ち上げる中心的な役割を担い、国内外の宇宙機関や研究機関の調整に携わりました。
2005年にJAXAでみちびき開発リーダーに
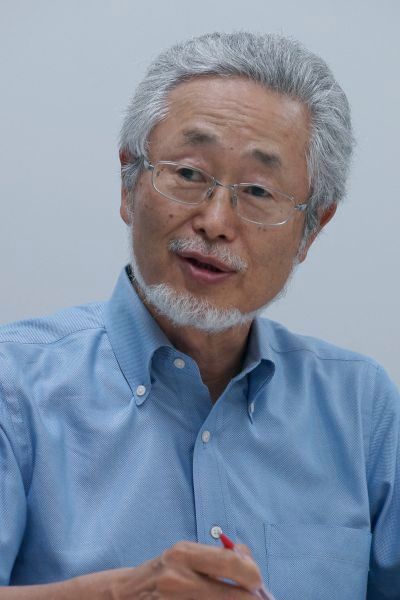
── 吉冨さんはいつ頃からみちびきに関わるようになったのでしょうか。
吉冨 JAXAの前身であるNASDA(宇宙開発事業団)で衛星開発や海外駐在事務、宇宙ステーションなどの業務に関わっていましたが、2005年4月からみちびきの開発リーダーとなりました。
── 当時、みちびきの計画はどのような状況でしたか。
吉冨 2002年に官民の協力で「準天頂衛星システム開発・利用推進協議会」が設置され、放送・通信サービスと測位という2つの機能を備えた衛星を準天頂衛星(みちびき)としていました。主に民間が放送・通信サービスを、国・JAXAが測位サービスという体制となっていました。しかし2004年に民間が撤退し、国のプロジェクトとして、測位サービスの衛星として仕切り直しをすることになりました。ちょうどJAXAは先行研究として高精度測位実験の研究開発を始めており、着任まもなく衛星測位システム室を立ち上げ、その室長も兼任することで、みちびきに関わるようになった訳です。
── その頃の印象に残っている出来事はありますか?
吉冨 2004年の10月に新潟中越地震が起きています。被災した長岡市の市長に宇宙技術の防災利用について切実なニーズを伺う機会がありました。夜間でも雲があっても地上の様子を知ることができるレーダー衛星が非常に重要ということで、これがその後のALOS-2(だいち2号)につながっていきます。そうした仕事と並行して関わっていましたので、みちびきにも防災の視点は欠かせないだろうと考えていました。
当時の米国は日本にとても協力的

── みちびきの測位機能は、GPSと互換性を持つ形で計画されてきました。
吉冨 みちびきでGPSと互換性を持つためにはアメリカ側からPRNコード(測位衛星の識別コード)を発行してもらう必要があります。当時のアメリカは欧州が立ち上げたGalileo計画をにらみながら日本を自陣に取り込みたいという思惑があったのだろうと思いますが、非常に協力的でした。第3世代のGPSで新設されるジャミングやマルチパスに強いL1C信号について、日本が信号を出すことをいち早く認めたばかりか、スペックの決定に当たって日本の受信機メーカーやチップメーカーなど関連業界の意向も知りたいと我々にリサーチを依頼してきました。日本からの提案もすごく前向きに受け止めてくれていました。
さらに測位を目的とするからには、それまでの地球観測衛星を上回る精度での軌道決定を行わなければなりません。少なくとも3~5cmの軌道精度が必要となるため、地上モニター局をなるべく地球上の離れた位置、それも8の字の軌道を東西南北から見るような位置に配置したい訳です。
南側はオーストラリアが協力してくれることになっていましたが、東側ではハワイでどうかということで調査に行きました。この際も米国務省や国防総省が全面的なバックアップのもとオアフ島やカウアイ島の施設を視察させてもらい、最終的にはオアフ島の北西にあるカエナポイントに地上モニター局を設置することになりました。
システム設計ではアンテナなどの問題を解決
── みちびき初号機の仕様や性能は、どのように固められていったのでしょうか。
吉冨 当初考えられていた放送・通信サービスは日本国内限定のものでした。一方、測位サービスも国内限定なのか、それともアジアやオーストラリアに展開するのか、大きな議論となりました。私自身は気象衛星ひまわりなどのように国際貢献の意味合いも含め、測位のサービスはアジア・オセアニア地域に幅広く提供すべきだと思っていましたが、一方でシステム設計の段階で問題も抱えていました。

なかでも大きな障害となっていたのが衛星のアンテナの問題です。地表で受信できる信号レベルを全ての衛星で揃える必要がある訳ですが、衛星から地表までの距離が近い衛星の真下と距離が遠くなる周辺部とでは、電波の強さと信号レベルが変わってしまうという問題がありました。ちょうどライトで照らした時、中央部分と周辺部で照度が違ってしまうのと似た問題です。これを周辺部が明るくなるように調整する必要がありました。
地表の凸に合うよう上手い具合に凹んだ電波の放射パターンにしたい訳ですが、3回の試作を経てもなかなか上手くいかなかった。「実現は無理ではないか。電波のビームを日本周辺に絞れば問題は解決する。測位サービスは日本周辺に限定するべきだ」という声も出てきた。税金でまかなわれるインフラサービスですから日本限定も一理はあるのですが、やはり「せっかくみちびきをやるんだったらアジア全体にサービスできるようにやるべきだ」と考え、アンテナ専業メーカーなどの支援を得ながらもう一度、挑戦することにしました。
そしてミッション機器担当のNEC東芝スペースシステム(現・NECスペーステクノロジー株式会社)が「ヘリカルアレイ・アンテナ」という素晴らしいアンテナを仕上げてくれました。19本のアンテナのうち中央の1本が強い電波を出し、周囲の18本で地表のカーブに沿うように放射パターンを凹型に調整し、受信範囲ならどこでも同じような信号レベルとなるというものです。このほかにもLバンドの進行波管を使う電源部分や、ルビジウム原子時計の調達にも苦労しましたが、何とかメドが立ったところで初代プロジェクトマネージャー(打ち上げ時も担当したJAXA寺田弘慈氏)に引き継ぎました。
プレーヤーが多く、調整が大変
── みちびきを開発し、システムを立ち上げていく難しさはどのような部分にあったのでしょうか。
吉冨 国だけで進めるプロジェクトになったとはいえ、非常にプレーヤーの多いプロジェクトであったことは間違いありません。文部科学省、総務省、経済産業省、国土交通省の4省の下にJAXA、情報通信研究機構、産業技術総合研究所、電子航法研究所、国土技術政策総合研究所、国土地理院とたくさんの研究機関が関わっています。さらに交通安全環境研究所や鉄道総合技術研究所が利用機関として参画するなどインタフェース調整が非常に大変でした。

運用に関しても、それまで通信衛星や地球観測衛星の追跡管制のノウハウがそのままでは通用しませんでした。測位衛星は軌道決定の頻度が多く、精度もさらに高めなければなりません。いろいろなモニター局から集まってくる軌道データを統合して軌道決定し、それを軌道情報として送信しました。独自に技術を磨き、それまで7cm前後だった精度を誤差3~5cmに高め、それが現在のみちびきの運用に活かされています。
── みちびきの現状についてどのような感慨を持っていますか?
吉冨 みちびきは宇宙基本計画において目玉中の目玉、一丁目一番地です。民間撤退や測位単独衛星としての再出発があり、ここまでこぎつけられたのは感無量です。ロードマップに示された4機体制、7機体制の整備が粛々と進み、日本だけでなくアジア・オセアニア地域の重要インフラとして信頼を得つつ定着していってほしいと願っています。
── ありがとうございました。
参照サイト
※所属・肩書はインタビュー時のものです。
-
 2017年03月27日
2017年03月27日NICT門脇直人:みちびきの通信機能の使命は、重要な情報を確実に伝えること
-
 2016年12月19日
2016年12月19日JIPDEC坂下哲也:身近なアイデアを実現すれば、みちびきはもっと便利になる
-
 2016年11月01日
2016年11月01日ゼンリン竹川道郎:地図情報は、自動運転を支援する“第2のセンサー”
-
 2016年09月28日
2016年09月28日科学警察研究所 原田 豊:防犯情報を地図に記録する『聞き書きマップ』を推進
-
 2016年08月22日
2016年08月22日防衛大学校 浪江宏宗:有益なシステムになるよう専門的見地から関わりたい
-
 2016年06月06日
2016年06月06日慶應大学 神武直彦:位置情報が様々なイノベーション創出に貢献する社会を実現したい
-
 2016年04月04日
2016年04月04日海上保安庁 石川直史:衛星測位と音響測距で海底の地殻変動を観測
-
 2016年03月28日
2016年03月28日ナビコムアビエーション 玉中宏明:ヘリコプターの測位でもSBASは重要になり得る
-
 2016年03月14日
2016年03月14日セイコーウオッチ 千田淳司:時計の3要素を満たすため、みちびき対応は必然だった
-
 2016年01月07日
2016年01月07日日本大学 藤村和夫:自動運転は、立場により考え方が違うからこそ法整備が必要
-
 2015年11月05日
2015年11月05日東京海洋大学 久保信明:アカデミズムの立場からみちびきを浸透させたい
-
 2015年08月26日
2015年08月26日セイワ 田邉正明:自社設計・海外調達生産による安価で高機能なカーナビを提供
-
 2015年08月19日
2015年08月19日横浜国立大学 高橋冨士信:孤軍奮闘のみちびきをスマートフォンから見守る
-
 2015年08月06日
2015年08月06日ニコン 小宮山 桂/山野泰照:位置情報は撮影した画像の楽しみ方を拡げてくれる
-
 2015年07月27日
2015年07月27日電子航法研究所 坂井丈泰:高い測位精度を実現する信号として普及を支援していきたい
-
 2015年07月14日
2015年07月14日シチズンTIC 斎藤貴道:国産衛星で正確な時刻を受けることが、安心につながる
-
 2015年07月07日
2015年07月07日国土地理院 辻 宏道:国土の状況を迅速に把握・共有するには衛星測量が欠かせない
-
 2015年03月23日
2015年03月23日測位衛星技術 鳥本秀幸:みちびきに最も必要な事は、ユーザー基盤の創造
-
 2015年02月27日
2015年02月27日ヤマハ発動機 坂本 修:衛星測位の信頼性向上で、無人ヘリのシステム設計も変わる
-
 2015年01月13日
2015年01月13日アイサンテクノロジー 細井幹広:測位精度の向上で、誰もが高度空間情報を使える社会を目指す
-
 2014年12月22日
2014年12月22日大林組 松田 隆:衛星測位の即時性を、施工管理や災害時の避難誘導に役立てる
-
 2014年12月01日
2014年12月01日パスコ 坂下裕明:高精度の衛星測位を活用し、より良い測位を安く提供する
-
 2014年10月21日
2014年10月21日測位航法学会 安田明生:世界トップレベルの衛星測位技術者の養成に貢献する
-
 2014年09月16日
2014年09月16日セイコーエプソン 森山佳行:ポジショニングをコア技術として、測位精度向上に期待する
-
 2014年07月01日
2014年07月01日経済産業省 武藤寿彦:企業を中心にみちびきのビジネスモデルを構築する
-
 2014年05月23日
2014年05月23日日本無線 脇 友博:みちびき対応の純国産ICチップを積極的に提供する
-
 2014年04月16日
2014年04月16日東京大学 中須賀真一:将来型の社会インフラで社会をどう変えるか検討する
-
 2014年03月03日
2014年03月03日SPAC 中島 務:民間企業によるみちびきの利用を促進し、普及に貢献する
-
 2014年02月03日
2014年02月03日JAXA 平林 毅:初号機の技術をさらに発展させ、みちびきを支援する
-
 2014年01月07日
2014年01月07日内閣府 野村栄悟:高精度の測位性能を活かし、国内外で戦略的な利用拡大を目指す