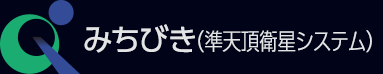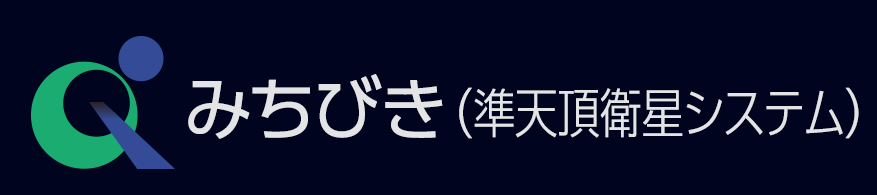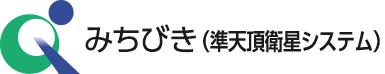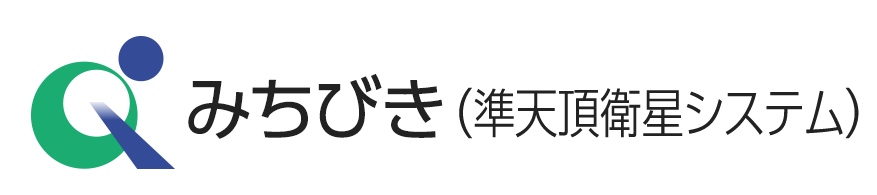東京海洋大学 久保信明:アカデミズムの立場からみちびきを浸透させたい
洋上でのナビゲーションに測位システムが欠かせないことから、東京海洋大学では長年にわたりGPS/GNSSの研究を進めています。研究室での取り組みのほか、人材育成やアジアとの連携について東京海洋大学(大学院 海洋工学系 海事システム工学部門)の久保信明准教授に聞きました。

少なくともGPSとQZSSは大丈夫という信頼感
── この分野の研究に携わるようになった経緯を教えてください。
久保 大学では電磁流体のコンピュータ・シミュレーションに関わっていました。航空宇宙分野に興味があり、「GPSを使った航空管制システムを計画」という企業のニュースを新聞で見かけ、記事に出ていたNEC(日本電気株式会社)の門を叩きました。
NECでは開発業務に携わっていましたが、大きなカルチャーショックを受けた出来事がありました。当時の上司とアメリカ西海岸のあるGPS受信機メーカーを訪ねた時のことです。規模は小さいですが社員の半分ぐらいが博士号を持っており、これと決めた分野でトップを走っている会社でした。同じものを作り続けているように見えて、30年も生き残っている開発型企業で、しかも社屋の前はすぐビーチ。ドアを開けるとサーフィンできる訳です。
大企業にいれば「この仕事がやりたい!」と思っても数ある中のワン・オブ・ゼムに過ぎませんが、小さい企業ならオンリー・ワンを追求できるのではないか。そういった考えもあって再びアカデミズムの世界に足を踏み入れてみようと、3年半在籍したNECを辞して東京海洋大学に来ました。
── GNSS/GPSが普及して世の中に定着していく上で必要なことは何ですか?

久保 すでに普及して定着しており、むしろ普通すぎて意識されなくなっていると思います。今後、一層大事になるのは「信頼感」だと思います。あくまで個人的な印象ですが、少なくともGPSとQZSS(みちびき)は絶対大丈夫だという信頼感があります。
何と言ってもアメリカは、対価を求めず20年以上サービスを続けてきました。SAも廃止を宣言し、それを守っています(SA:Selective Availability。GPSの測位精度を意図的に落とす措置。2000年5月に解除された)。一般への普及を考えると、こういう積み重ねで醸成される信頼感が一番大事です。いつなくなるか分からないシステムは使えないし、他のGNSSシステムがGPSほど信頼されていないのは、そういった懸念をまだ拭い切れていないからだと思います。
みちびきもきちんと5年間にわたって運用を続け、情報をオープンにし無償で提供しています。この姿勢はやっぱり海外で評判がいいですね。アジア地域だけでなくヨーロッパの研究者も関心を持っています。機数は少ないながら信頼は得ており、あとはロードマップのとおり4機、7機と体制を充実させていくことで、現在得られている信頼感がもっと強固なものになっていくと思います。
日本がリターンを得る部分をどう組み立てるか
── 測位衛星は税金で運用されるインフラですが、無償開放という姿勢とどう折り合いをつけていったらいいのでしょう。
久保 ナショナルセキュリティに関わるインフラでありながら、ずっとフリーで使えるという信頼感が醸成されている。考えてみれば不思議な話です。フリーと言いながら、最初に走っているアメリカはそれなりの利益を得ています。フリーであることで恩恵を受けるのはコストを負担していない側かと思ったら、逆にアメリカだったりするんです。受信機の特許など調べていくと、やはりオリジナルな部分はしっかり押さえており、世界に普及すればアメリカが潤うような仕組みになっています。
みちびきもフリーで使ってもらって普及を進める部分と、日本がリターンを得る部分をどう分けていくか、どう組み立てていくかが課題となるでしょう。難しい戦略が必要ですが、きっと可能と思います。国民の税金で運営されているシステムですからね。

そのために私たちアカデミズムの人間ができることの1つは、国際学会などに参加して研究成果をアピールし、日本のプレゼンスを示していくことです。企業にも優秀な方がたくさんいますが、論文を書いて発表することはなかなかできません。一方、国際学会の本流は、スタンフォードやオハイオ州立大など有名大学を通じ人脈的にもDOD(Department of Defense、米国国防総省)ともつながっている。そうした人たちに「日本にもこれぐらいの技術力はあるんだよ」と見せておきたい。決してフリーの信号にタダ乗りして商売しているだけじゃないと言いたいですね。自由に研究発表すれば、多少技術は盗まれるかもしれません。けれども自由闊達に対等な議論をして、そうしたコミュニティとつながっていくことは、それ以上に重要なことです。
3大学が連携するG-SPASEは大きなウェイト
── 人材育成の取り組みについてはいかがでしょう。
久保 日々の講義やゼミはもちろん、意識して学生をできるだけ学会に連れていくようにしています。さらに大きなウェイトを占めているのが、東京大学、慶應義塾大学と東京海洋大学の3大学連携でのG-SPASE(宇宙インフラ利活用人材育成のための大学連携国際教育プログラム)という活動です。
東京大学の柴崎亮介先生、慶應義塾大学の神武直彦先生とご一緒させていただき、1大学ではできないレベルでの活動ができています。特にアジアの主要大学との協力関係の構築は、非常に重要な任務だと思っています。その国のしかるべき大学の先生方は、国の意思決定に近いところで関わっています。そういう方々には当然ながらヨーロッパからも中国からもアプローチはあります。そんな中で我々は「日本は信頼できる国だ」と分かってもらおうとしています。

私自身も非常に勉強になるのは、柴崎先生と渡航し、現地の政府高官や大学関係者との会合にご一緒させていただき、講演を聞かせてもらうと、それはもう素晴らしい講演をされる訳です。いったんスイッチが入った柴崎先生は「基準点を建てたらこんなメリットがある」「日本と仲良くするとこんないいことがある」と、まさに日本そのものを背負っているかのごとく、すさまじい説得力を発揮します。正に味方を増やすための「戦い」です。こういうことを、学生たちにも事あるごとに伝えていこうとしています。
ともあれ「G-SPASE」の取り組みは、まずは3大学でスタートし、非常に上手く機能していると思います。将来的には大学共同利用施設として、GNSSに関連する研究をしたいという学生をどこからでも受け入れられる仕組みができると素晴らしいなと思います。
── GNSSやみちびきの更なる普及に向けて、どんな将来イメージをお持ちですか?
久保 学生と話していても、GPS/GNSSが大事なものであることは分かっていますね。身近なカーナビやスマホなど、あらゆるところに使われていますから。そういう意味では、定着させようと無理に思わなくても自然に広がっていくと思います。
一方、みちびきに絞ってみると、衛星測位システムは気象衛星などのように成果物を見せられるものではなく、みちびきという名前もまだ浸透しているとは言えません。ただ、現在1機が上手くいっている。こうした例や、得られる効果を実際に見せていくことが重要です。4機、7機と整備していく訳ですから、それを確実に遂行し、補正データも確実に送信していくことが定着の鍵となります。
── ありがとうございました。

研究室がある越中島キャンパスの校舎屋上で。手前は衛星信号の受信アンテナ
※所属・肩書はインタビュー時のものです。
-
 2017年03月27日
2017年03月27日NICT門脇直人:みちびきの通信機能の使命は、重要な情報を確実に伝えること
-
 2016年12月19日
2016年12月19日JIPDEC坂下哲也:身近なアイデアを実現すれば、みちびきはもっと便利になる
-
 2016年11月01日
2016年11月01日ゼンリン竹川道郎:地図情報は、自動運転を支援する“第2のセンサー”
-
 2016年09月28日
2016年09月28日科学警察研究所 原田 豊:防犯情報を地図に記録する『聞き書きマップ』を推進
-
 2016年08月22日
2016年08月22日防衛大学校 浪江宏宗:有益なシステムになるよう専門的見地から関わりたい
-
 2016年06月06日
2016年06月06日慶應大学 神武直彦:位置情報が様々なイノベーション創出に貢献する社会を実現したい
-
 2016年04月04日
2016年04月04日海上保安庁 石川直史:衛星測位と音響測距で海底の地殻変動を観測
-
 2016年03月28日
2016年03月28日ナビコムアビエーション 玉中宏明:ヘリコプターの測位でもSBASは重要になり得る
-
 2016年03月14日
2016年03月14日セイコーウオッチ 千田淳司:時計の3要素を満たすため、みちびき対応は必然だった
-
 2016年01月07日
2016年01月07日日本大学 藤村和夫:自動運転は、立場により考え方が違うからこそ法整備が必要
-
 2016年01月03日
2016年01月03日日本宇宙フォーラム 吉冨 進:アジア・オセアニアの重要インフラとして定着してほしい
-
 2015年08月26日
2015年08月26日セイワ 田邉正明:自社設計・海外調達生産による安価で高機能なカーナビを提供
-
 2015年08月19日
2015年08月19日横浜国立大学 高橋冨士信:孤軍奮闘のみちびきをスマートフォンから見守る
-
 2015年08月06日
2015年08月06日ニコン 小宮山 桂/山野泰照:位置情報は撮影した画像の楽しみ方を拡げてくれる
-
 2015年07月27日
2015年07月27日電子航法研究所 坂井丈泰:高い測位精度を実現する信号として普及を支援していきたい
-
 2015年07月14日
2015年07月14日シチズンTIC 斎藤貴道:国産衛星で正確な時刻を受けることが、安心につながる
-
 2015年07月07日
2015年07月07日国土地理院 辻 宏道:国土の状況を迅速に把握・共有するには衛星測量が欠かせない
-
 2015年03月23日
2015年03月23日測位衛星技術 鳥本秀幸:みちびきに最も必要な事は、ユーザー基盤の創造
-
 2015年02月27日
2015年02月27日ヤマハ発動機 坂本 修:衛星測位の信頼性向上で、無人ヘリのシステム設計も変わる
-
 2015年01月13日
2015年01月13日アイサンテクノロジー 細井幹広:測位精度の向上で、誰もが高度空間情報を使える社会を目指す
-
 2014年12月22日
2014年12月22日大林組 松田 隆:衛星測位の即時性を、施工管理や災害時の避難誘導に役立てる
-
 2014年12月01日
2014年12月01日パスコ 坂下裕明:高精度の衛星測位を活用し、より良い測位を安く提供する
-
 2014年10月21日
2014年10月21日測位航法学会 安田明生:世界トップレベルの衛星測位技術者の養成に貢献する
-
 2014年09月16日
2014年09月16日セイコーエプソン 森山佳行:ポジショニングをコア技術として、測位精度向上に期待する
-
 2014年07月01日
2014年07月01日経済産業省 武藤寿彦:企業を中心にみちびきのビジネスモデルを構築する
-
 2014年05月23日
2014年05月23日日本無線 脇 友博:みちびき対応の純国産ICチップを積極的に提供する
-
 2014年04月16日
2014年04月16日東京大学 中須賀真一:将来型の社会インフラで社会をどう変えるか検討する
-
 2014年03月03日
2014年03月03日SPAC 中島 務:民間企業によるみちびきの利用を促進し、普及に貢献する
-
 2014年02月03日
2014年02月03日JAXA 平林 毅:初号機の技術をさらに発展させ、みちびきを支援する
-
 2014年01月07日
2014年01月07日内閣府 野村栄悟:高精度の測位性能を活かし、国内外で戦略的な利用拡大を目指す